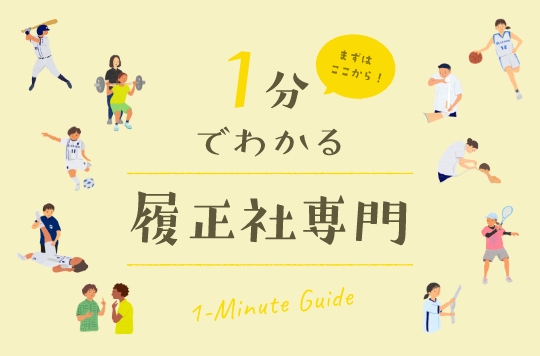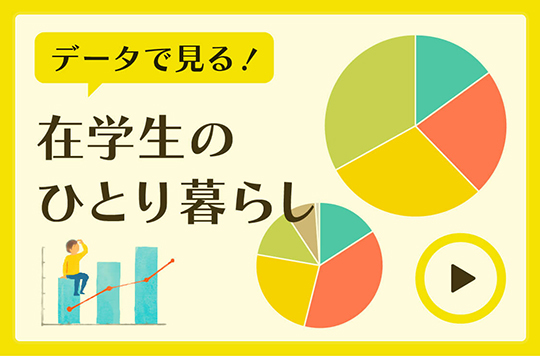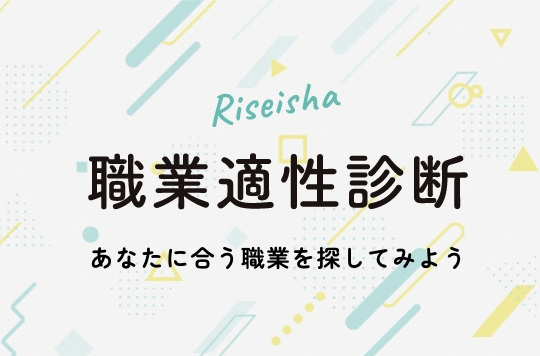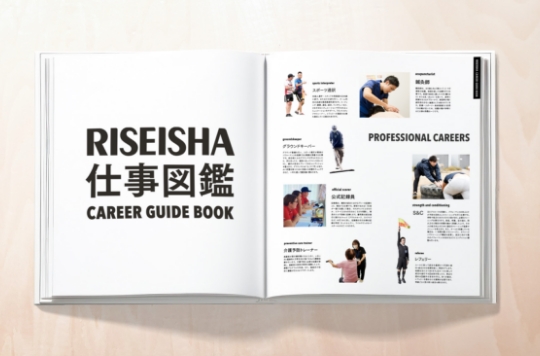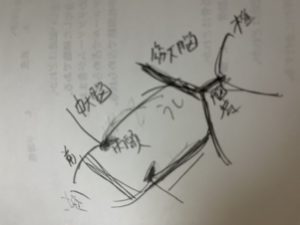過去にもこう言うテーマでブログを書きましたが、
最近また学生に聞かれたので過去ブログ読んでね!
と言いたかったけど言わなかった先日の私と、
またそういうテーマでブログを書く今の私です。
それまでの学習習慣も年齢もそれぞれ違うので
万人に最善な方法を一様に語ることはできないので
「人それぞれ」という結論に至りますが、
だからこそいろんな教員に学生時代に
どんな勉強していたか聞いて回るのも
面白いかもしれませんね。
何がヒットするかわからないので、以前の
ブログとなるべく違う視点で自分がやっていた
勉強法を今回ご紹介しようと思います。
このブログの画像でもそうですが絵に描きながら
勉強することが自分は今も昔も多いです。
こちらは自分が学生時代過去問で勉強していた
時の書き込みです↓↓↓↓↓↓
絵を描いていると「あっ、あの構造物も描かなきゃ」
と意識して図示するようになるので、教科書や
プリントの図を眺めて覚えるよりも自分的には
頭に入ってきやすかったです。
なので学生にも絵を描くよう勧めてるんですが
7割くらいの確率で「絵心ないんで…」って断られます。
絵心はあった方がいいけどたとえ絵心がなくても
図示したらええんやで!!!
↓こちらはテスト頻出の脳の血管を図示したものです。
「後交通動脈」って書くのもめんどくさく、
「後」すら画数が多いからって「うし」って
なんですのん…と思わないではないですが、
絵を描いて覚えるってほんとこのレベルの画力で
十分だと思っています(学生時代に描いたものなので
線が生えてる場所にちょっと甘いところが
ありますが……)
絵描き歌のようにいつも同じ書き順で描いていると
手が覚えてくるので考え込まなくても描けるように
なってきます。
描けるようになったら「○○は何本あるか」という
問題は描いた図の線の本数を数えればいいので
丸暗記しなくてもいい事項になります。
脳の容量に自信がない自信しかなかったので、
暗記科目のためにそこ以外の部分で脳の容量を
いかに空けとくかという工夫を頑張っていました。
次回は授業用ノートの中身をご紹介しながら、
自分がやっていた脳の容量を空けておく工夫を
お伝えしたいと思います。
日々の勉強のヒントに何か一つでもなることを願って!