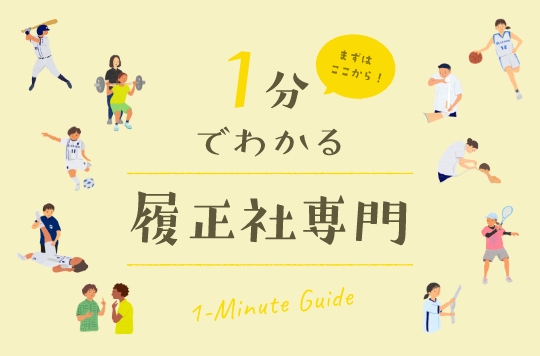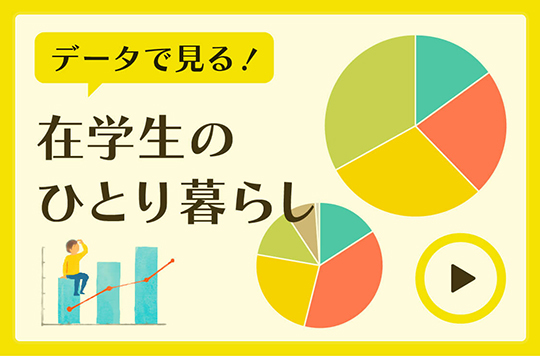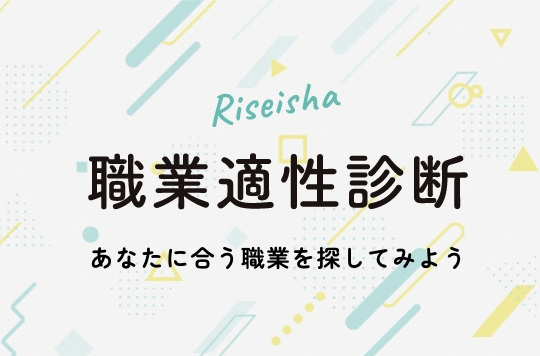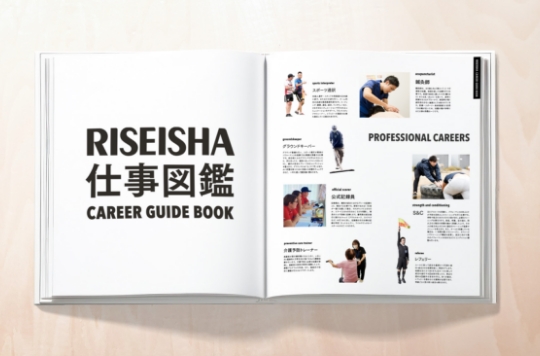皆さんこんにちは、教員Zです!
まだまだ寒波の勢いが強くて、明け方の地冷えは相当堪えますね!
今朝、通勤(通学?)途中の近所の川では、表面が氷板で覆われていました…
さてさて、話題は変わりますが、久しぶりに古代九鍼の続編をしたいと思います。延び延びで申し訳ありません…
今回は、「刺入する鍼」の解説をしたいと思います!
毫鍼(ごうしん)
寒熱の問題や痛み・しびれの問題に用いられます。
これは、現在多くの鍼灸師に使われている鍼の原型になったものです。と言いますか、今でも毫鍼と言います。
鍼の太さ(直径)や長さ(寸法)を変えると長鍼や大鍼としても使えますし、接触させたり摩擦したりすると員鍼やてい鍼としても使える万能鍼です!
員(円)利鍼(えんりしん)
これは急激な痛み・しびれの部分に対し、深く刺します。
長鍼
これは深い部分の邪気や、痛み・しびれを取るのに用いられます。
(上は毫鍼)
大鍼
当時は、関節水腫の水抜きに用いられてました。
(上は長鍼)
お馴染みの語呂合わせですが、
『強引(毫鍼)に刺入するのは遠慮(員利鍼)してちょう(長鍼)だい(大鍼)!』です!
古代九鍼は次回の其の四で終了となります!
乞うご期待下さい!