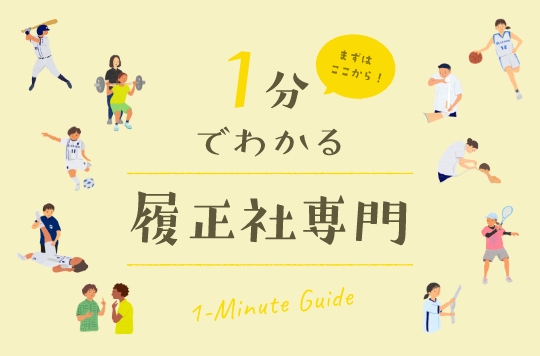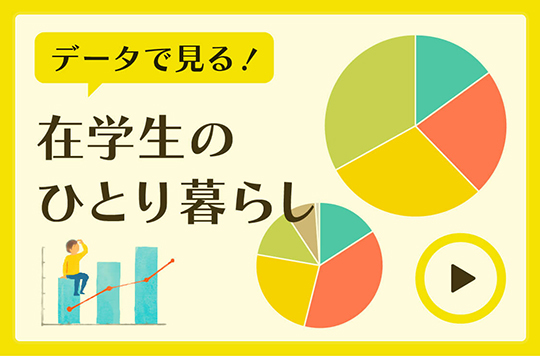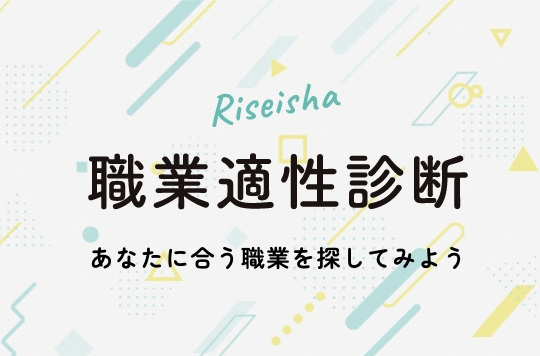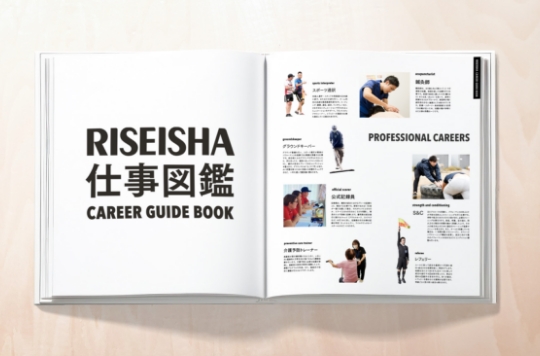こんにちは!教員Zです!
本日は昨年の10/25から始まった「古代九鍼」シリーズの最終回となります!
たった4回の内容で4ヶ月半も掛かってしまいました…。
1回の内容に費やした時間は、ざっと1ヶ月ですね…
ということで今回は、3つ目のカテゴリーである『体内に刺入せず、皮膚に接触あるいは摩擦する鍼』について説明したいと思います!
種類は2種類です。
1.てい鍼
古代中国では、主に手の指や足の指の先っぽにあるツボ(正式には井穴〔せいけつ〕)に対し、この鍼を当てることで正気(身体に必要な、新鮮で活力のある気)を補ったり、はたまた邪気(流れの悪くなった、身体に不必要な古い気)を体外に出したりするのに用いていました。
もちろん現代でも同じように使いますが、手の指や足の指の先っぽにあるツボにこだわらず、色んなツボにも用いられています。
曲がりなりにも鍼という名前なだけに、刺さないのはちょっと不思議に感じますかね?
まあこの辺の考え方については、次回以降においおいやって行きましょう!
(更新が、また伸びそうでね…笑)
2.員鍼
こちらの鍼は、分肉(分肉=肌肉です。肌肉には、1:皮膚と皮下組織・脂肪、2:体表に接する筋肉、などの意味があります)の間、つまり体表のとても浅いところをこすって邪気を体外に出させます。
指圧棒的な側面もあるのでしょうね!
ではお決まりの語呂合わせ!
「もう庭(てい鍼)園(員鍼)に刺入しないで!」
もひとつおまけに豆知識!
足少陽胆径の陽輔穴の別名を、『分肉』といいます。
古代中国人は、意味もなくむやみやたらに経穴名は付けませんよ!
なんでこの経穴が分肉(=肌肉)なんでしょう?
これは身体の陰陽(前後)の中間である半表半裏の位置に胆経が存在しているのがポイントですね!
肌肉も体表の皮膚(陽)と皮下組織の更に下にある器官など(陰)の中間のものです。
胆経は、そこへの作用が強い経絡と言われています(陽輔穴は特にその作用が強いのかもしれません)。
これは昔鍼の師匠に聞いたのですが、古人は気胸の時には外界と接している肺も肌肉系と考え、陽陵泉に灸をすえ、肺表面を引き締めて対処していたそうです
(今は当然病院へ直行ですよ!)。
また金瘡(刀傷)には、陽交・外丘(もちろん胆経)と、脈診の大家:藤本和風師は喝破されていたそうです。
これも肌肉(半表半裏)の治癒に使う一つの例ですね!