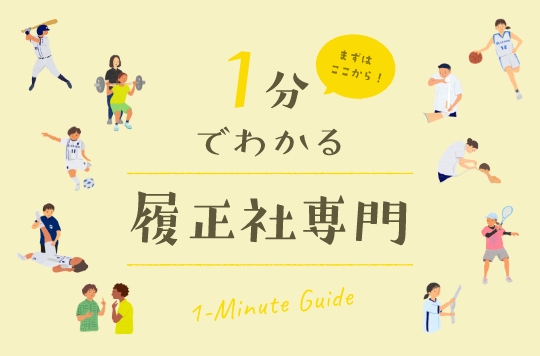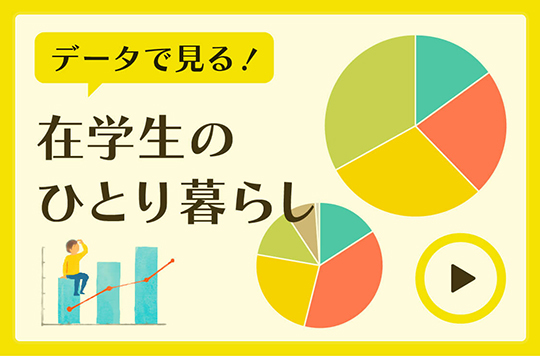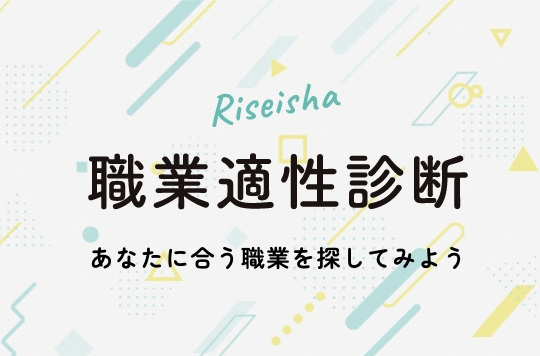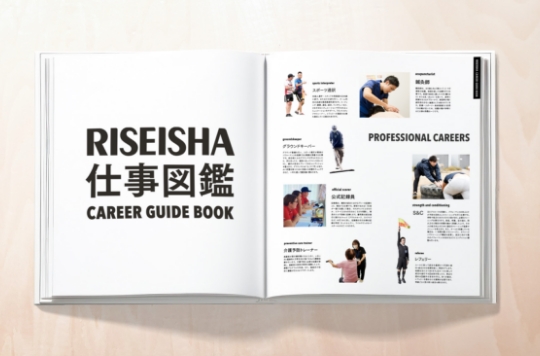今回のぷらり旅は・・・・
遷都1300年を迎えた「奈良」。
できるだけ鹿のいるところは避けて・・・・
近鉄奈良駅の少し手前、大和西大寺から2駅ほどいったところに
世界遺産にも登録されている
「薬師寺」、「唐招提寺」がある。
唐招提寺の敷地内にある「新宝蔵」には数多くの仏像がまつられている。
1体1体を順に見ていく中で、ふと、解説が目に留まった。
そこには、
「この仏像は少し身体を左に捻っている」というようなことが書かれていたように覚えている。
この仏像の前から、しばらく動けなくなった。
実際によ~く観察してみると、次のようなことに気がつく。
1)右と左のウエストのくびれている位置が違う
2)足の裏への体重のかかり方(配分)が違う
3)身に着けている衣の皺のより方が右と左で違う
4)骨盤の左右の傾き方が違う
などなど、確かに左に身体が捻れている。
そして、一番、気づいたことはこの仏像をつくりあげた人の観察力である。
「観察力」って柔道整復師に必要?
患者さんを前にして行う「視診・触診・検査」といわれるものはすべて観察です。
施術の前と後には必ず患者さんのその日の状態(様子)を観察します。
観察力は柔道整復師にとって最も必要な力です。
「ちょっと待てよ?」「あっ、そうか!!」を大切にする。
自分の立つ位置を、目線を、変えると見え方が変わる。
人のちょっとした動き、ちょっとした仕草、それぞれに意味がある。
柔道整復師として患者さんに向かうとき、
患者さんのちょっとした動き、ちょっとした仕草に気づけるようになりたい。
改めて、「みる」ことの大切さに気づかされた。
そんな、ぷらり旅でした。