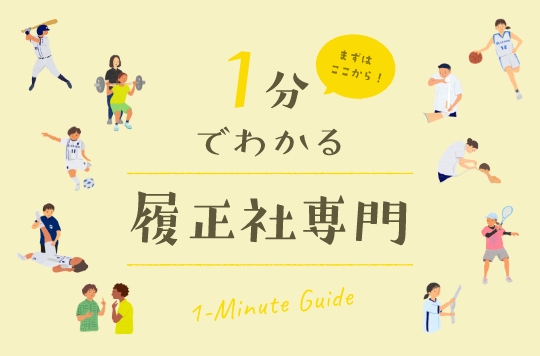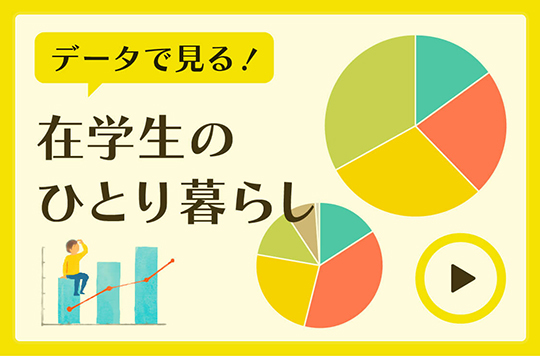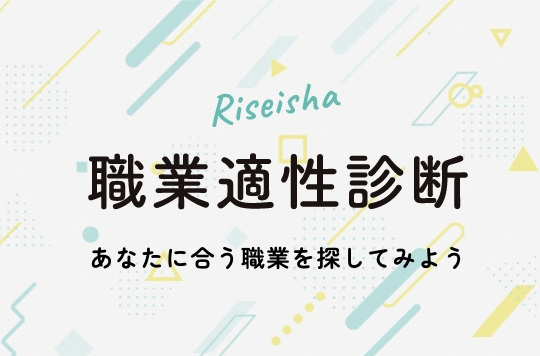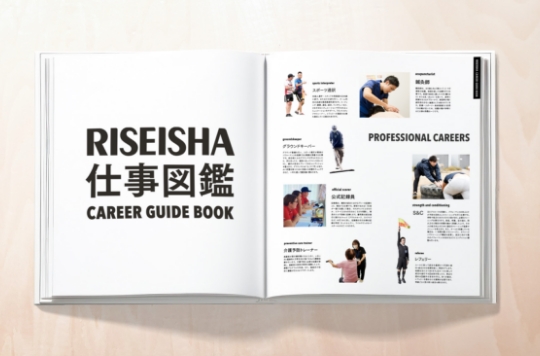本校では、2年生になると疾患を知る授業として、
整形外科学(骨、軟骨、筋、靭帯、神経などの疾病・外傷を主として手術的処置などにて治療を行うもの)、
内科学(内臓に起因する疾患を主として薬物療法や食事療法などで治療を行うもの)、
神経内科学(脳血管障害や、アルツハイマー病に代表される認知症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症 等の変性疾患、皮膚筋炎・多発性筋炎等の筋疾患、ギランバレー症候群を始めとする末梢神経障害、中枢神経系感染症およびてんかん・頭痛 等の機能性疾患などを主として内科治療を行うもの)、
精神医学・臨床心理学(心を中心とした疾患について、医療人としての対応を学ぶもの)などを学び、
個々の患者様にあった理学療法治療を考えていきます。
そして、それらの疾患に対しての治療として運動療法や物理療法や
日常生活活動(ADL)の指導などについて学んでいます。
もちろん、これら以外にも学んでいる科目はありますよ。
今回は、この中よりADL授業の受講風景をお伝えします。
この科目は、理学療法の治療対象となる各疾患由来の障害に対して、
現状の機能や、補助する機器などを用いての生活方法の指導を中心に修学しています。
そこで最初に、理学療法士の対象となる基本的動作について学んでいます。
基本的動作とは、寝ている姿勢での寝返り動作や、その姿勢からの起き上がり動作、
起き上がってからの座位姿勢保持動作、そこからの立ち上がり動作や立位保持動作、
立位での歩行を中心とした移動動作、
歩行が困難な状態での車椅子移動(ここには、乗り移り動作となる、移乗動作が含まれます)。
各動作で必要となる安全で円滑に姿勢保持や姿勢変換が可能となるためには、
各姿勢での体を支える能力を知ることが重要となります。
写真の状況は、立ち上がりにつながる
片膝立て位での安定性を前後・左右から外乱を加えて確認しています。
体を支えるためには床面への接地面積が広いこと(これは、支持基底面といいます)。
そして、その支持基底面内に身体重心があることが大事です。
これを学ぶために、学生同士で様々な姿勢にて外乱負荷を掛け合いながら自身の
身体を通じて学ぶワークをしています。
理学療法士は、障害に伴う動作困難を治療していくエキスパートです。
なので、まずは体感を通じて学びを深めています。
寝ている姿勢での動作困難の原因は、実は歩行のように身体重心を高い位置でコントロールする
動作困難の原因と共通していることが多いです。
学生たちが、多くの知識や技術を習得し、患者様の問題解決ができる
医療人へ成長するのを日々たのしみにしています。