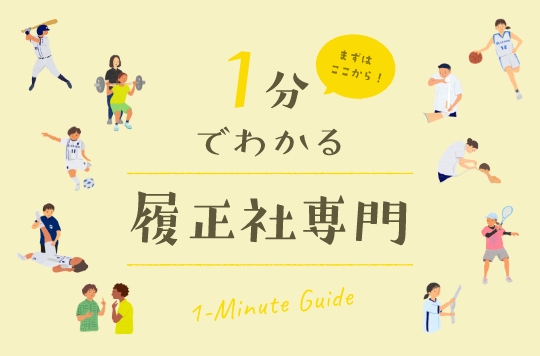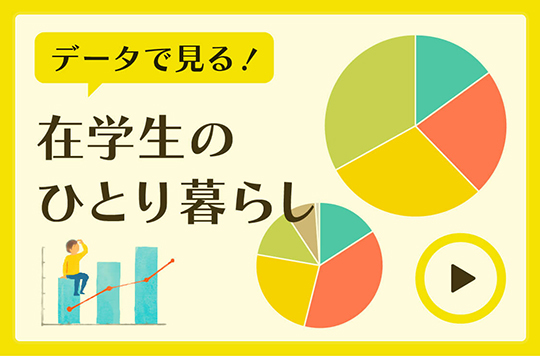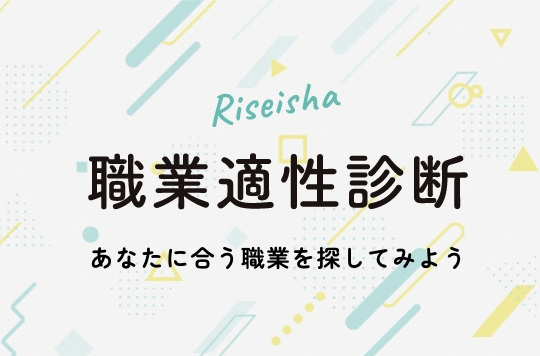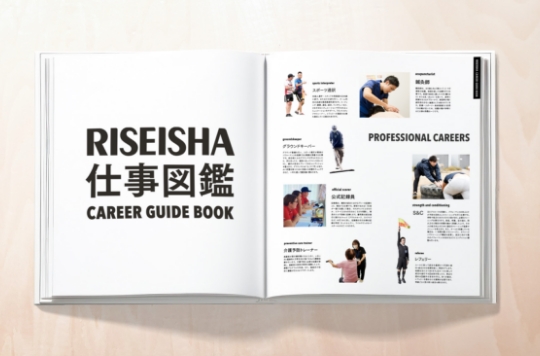今回、解剖学実習の実技試験を見学させていただきました。
解剖学実習は、1年生の解剖学で学んだ全身の骨、筋を体表から視診、触察する技術の習得を目標として学ぶ科目です。
試験は受験者がペアの学生を伴う形で行われますが、検査する側の人を〝検者〟検査を受ける人を〝被検者〟と言うそうです。
先生の開始合図とともに、検者が被検者に体勢等の指示を出して、動き始めました。

目的の部位を見て、動かして、触れて確認しているようです。
そしてペンを手に取ると、被検者の身体に直接線を引きはじめました。

この実技試験では、出題された部位を身体に直接書き込んでいくそうです。
驚いたので後で先生に聞いたところ、解剖学実習では普段の授業でも骨や筋の走行をペンで身体に書くとのこと。
もちろん人体の構造は教科書に詳しく載っていますが、あくまでもそれはオーソドックスなもの。
人によって骨や筋の付き方も異なるため、実際に人の身体に書き込むことで、より実践的な知識や技術が身につくということですね。
そして、正しい位置に線が引けているかどうか、先生が採点してまわります。


こうして学生が実際に身体に引いた線を見ることで、認識のずれも発見しやすいとのこと。
また、授業中にはペンで色分けして骨や筋の境目、位置関係を把握しやすくしているそうです。
目に見えない部分を正確に把握するということはとても難しそうですが、非常に興味深い実技試験の様子でした。
理学事務 松原